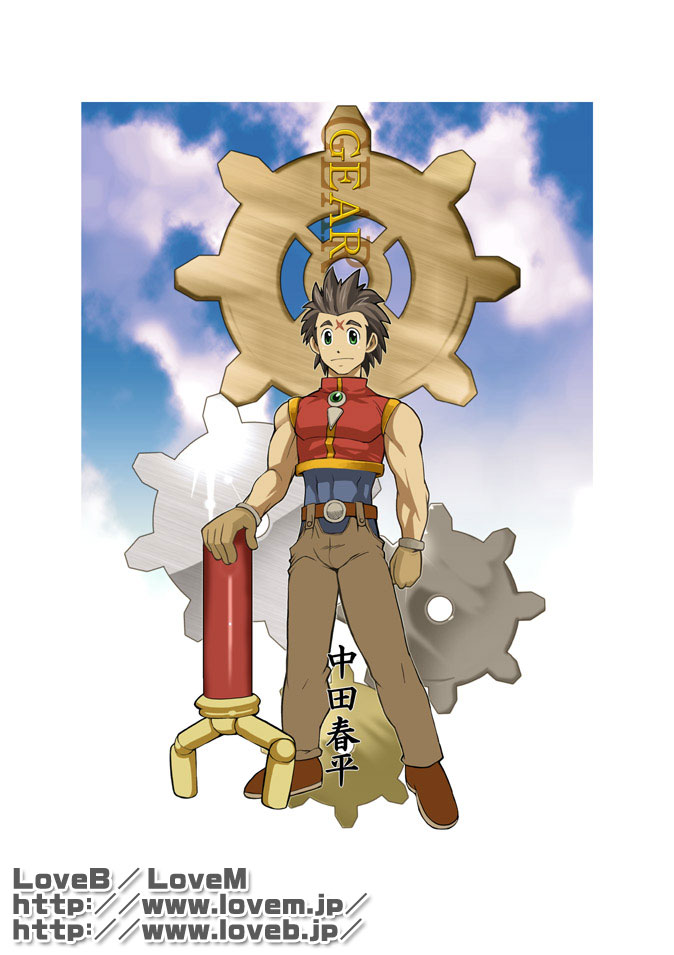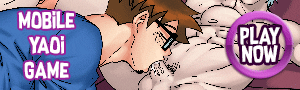[JPN] Shunpei Nakata 中田春平 – 一枚上手
1.
田上勇一は、最近仕事帰りに週二回のペースで、会社近くの駅ビルにあるスポーツクラブに通っている。
半年前の四月、勇一が勤める証券会社の人事異動で、勇一はそれまでの営業から、ネットでの企業情報収集を業務とするファイナンス・ディーリング部に移動になった。そのため、勇一は一日中パソコンの前で仕事をしなければならなくなり、ストレスと運動不足解消のためにこのクラブに通うようになったのだ。
その日もいつものフィットネスコースをこなしたあと、勇一がスポーツクラブの風呂に入っていると、大柄の体躯に濃い体毛を茂らせた男が、がらりと扉を開けて、浴室に入ってきた。
その男安岡大吾は、湯船に浸かっている勇一の姿を見つけると、包茎気味の巨大な一物をぶらぶらと股間で揺らしながら、勇一の目の前に寄ってきた。
「うぃーっす、田上ちゃーん」
ざっと一回かけ湯をして、大吾はそのまま浴槽に遠慮なくざぶりと入ってきた。どうやら大吾には、全体的にあまり細かいところにこだわらないところがあるようだ。
「ああ、安岡さん、今日は来てたんですか」
隣に寄ってきた大吾は、あっさりとした勇一の言葉に、
「『来てたんですか』はねーだろ、おい……」
そう言って、大げさに顔をしかめた。
が、それ以上後を引くこともなく、大吾はまた悪戯っぽい表情を作ると、
「ところで田上ちゃん、ムスコさんのほうは元気かーい」
そう悪びれもせず、湯舟の中で勇一の股間に手を伸ばし、無骨な指先でぐにぐにと勇一の一物を揉みしだいてきた。
「や、やめてくださいよ……」
勇一が困った顔を作り、軽く大吾を睨みつけると、大吾は大きくて四角い顔を子供っぽくゆるめ、
「いやすまんすまん、大学時代からの癖でなあ。他人のチンポ見ると、ついついいじりたくなっちまうんだ」
そう言い訳をすると、へへ、と照れ笑いを浮かべた。
そして、大吾は浴槽の湯でざぶざぶと顔を洗うと、突然大学時代の話をし始めた。
大吾は当時応援団に在籍しており、最終的には団長まで勤め上げたという。そして、その応援団には「女子との交際禁止(風俗も含め)」という鉄の掟があったらしい。
とは言うものの、性欲が盛んな学生たちのこと、とても「その行為」を我慢できるはずもなく、いつしか先輩から後輩に対して「しごき」という名目で、集団オナニーや先輩たちの一物の尺八を強制させる行為が団内でまかり通っていたのだそうだ。
「先輩には逆らえねえしな。俺も一年坊主の時は、部室で下だけ全部脱いだ先輩たちの先汁と汗で蒸れておっ勃ったくっせえチンポを一本一本無我夢中でしゃぶりあげてなあ。全員が汁をぶっ放すまで終わんねえんだ、これが」
大吾はそう言って、口の前に右手で作った筒を持ってきて、それへすぼめた唇を前後させた。
もともと大吾はエロ話が好きなようで、なんの前振りもなくそういった話をする。
そんな卑猥な身振り手振りでその様子を再現する大吾は、まるで性欲盛りの高校生のようだ。
浴槽から上がっても、大吾は遊び半分にポーズを取りながら、ふんっ、ふんっ、と、全身の毛深い筋肉に力を込めて、自慢のそれを誇らしげに鏡に映している。
二十八歳の自分よりも三歳年上なのにどこか子供っぽい大吾が、一人っ子の勇一にはまるで兄のようにも、弟のようにも思えていた。
勇一と大吾がこのスポーツクラブで出会ったのは、今から三か月ほど前になる。
その後、親しくなってから勇一が聞いたところによると、大吾は酒屋の次男坊で、高校生のころからずっと実家の手伝いをしているという。勇一と同じく現在独身で、休日には同じ町内会のオヤジたちを集めた草野球チームの監督をしているそうだ。最近やや腹が出てきたのと、体力の衰えを感じつつあるのが、このクラブに通うようになった理由らしい。
ちなみに、勇一は大吾のことをずっと「安岡さん」と呼んでいるのだが、大吾は勇一と初めて会ってから二回目にはもう勇一を「田上ちゃん」と呼んでいた。
無精ひげ面ににっかりと笑顔を浮かべて、勇一をそう呼ぶ大吾は、まるで長年の親友でもあるかのように親しげな口をきく。
そして、この日も勇一は大吾に誘われ、駅の東口近くにある小料理店・風俗店が立ち並ぶ路地の裏にある、大吾いきつけの小さな焼き鳥屋『てっちゃん』に入った。
そこはいかにも大吾が好みそうな、そこそこに小汚いが値段もそこそこで、それなりにうまい物は食わせてくれる店だ。
「……野球の助っ人……ですか? 僕が」
テレビで野球中継が流れる店内で、勇一はつくねの串を右手に持ったまま、あんぐりと口を開けていた。
「ああ、こんなこと頼めるのは田上ちゃんしかいねえんだよ」
そう言って、大吾は一気に焼酎をあおった。
「次こそは我が『ビッグゴールデンボーイズ』の連敗記録をなんとしても止めなければならんのだっ!」
今週末の土曜に、大吾が監督をしている草野球チーム「ビッグゴールデンボーイズ」と隣町のチームとの試合があるそうなのだが、大吾のチームのメンバーで寿司屋の兄弟二人が、急に親戚に不幸があって出場できなくなったのだという。
「代わりのメンバーを八方手を尽くして探したんだが……どうしてもあと一人足りねえんだ」
酔いが回ってきたのか、興奮しているのか、大吾は汗まみれのゆでだこのような顔になっていた。
「でも、僕……体育の授業以外で、一度も野球やったことないし、そんな、試合なんて……」
「いいっていいって。もうこの際、うまいとか下手とか、そんなんは二の次だ。田上ちゃんはただユニフォーム着て、グラウンドとバッターボックスに立ってくれればいい。その分俺たちがフォローするから。なっ」
そう言って大吾は勇一の目の前で両手を合わせ、拝み込むように頭を下げた。
そこへ、それまで黙って焼き鳥を焼いていたはげ頭の店主が、突然口を出してきた。
「お兄さん、大ちゃんのお願い聞いてやってよ。大ちゃんとこにはうちもオヤジの代から世話になってんだからさ」
「大ちゃん」と呼ばれた大吾は、決まり悪げにぼりぼりと頭を掻いた。
「おやっさん、そろそろその『大ちゃん』ってのはやめてくれよ……。俺もう三十一なんだからさぁ」
そして、大吾は声を潜め、勇一に、
「ここな、俺んとこの酒屋の昔からのお得意さんなわけよ。俺も高校生んころから配達でしゅっちゅう出入りしててな。だからいまだにガキ扱いってわけだ」
それへ追い打ちをかけるように店主が、
「もしお兄さんが引き受けてくれたら、今日の勘定安くしとくよっ」
「だからぁ、おやっさんは黙って串焼いててくれよっ」
すでに、勇一が大吾の申し出を断れるような雰囲気ではなさそうだ。
2.
それから三日経った、土曜日の夕方。
誰もいなくなった区営グラウンドの更衣室で。
草野球の試合が終わり、大吾と勇一は、泥だらけのユニフォームをのろのろと着替えていた。
試合結果は、五十六対〇。「〇」のほうが、大吾たちのチームである。
あまりのボロ負けっぷりに、試合後恒例の「懇親会」(という名の飲み会)も行われないまま、『ビッグゴールデンボーイズ』のメンバーは早々にグラウンドを後にした。
すでに勇一の着替えは済んだが、大吾はまだ、汗で汚れたシャツとブリーフ姿のままだ。
そして、大吾は長椅子にガタンとでかい尻を置くと、
「……ちくしょう」
肩を落として、大きくため息をついた。
そんな大吾の姿を見ていた勇一は、
「安岡さん……」
「……ん」
「これから『懇親会』、しませんか。僕たちだけでも」
思わずそう、声を掛けていた。
二時間後、『てっちゃん』にて。
「ははは、じゃあ、お兄さん、空振りしたのに塁に出たってわけですか。しかも三塁に」
うまそうな匂いをさせ、じゅうじゅうと音を立てている焼き鳥を器用にひっくり返しながら、店主は穏やかな笑みを浮かべた。
「だから僕、最初から野球のルールはなんにも知らないって言ったじゃないですか……」
勇一は、そう言って肩をすくめた。
大吾はやけ酒なのか、さっきからガバガバと何杯も焼酎を喉に流し込んでいる。
「……」
掛ける言葉もない、というのはこういうことを言うのだろうか。
(怒ってるよな……安岡さん)
やはり、大吾にはきちんとした言葉で謝罪したほうがいいのではないか。
そう、勇一が考えていたとき。
突然、真っ赤な顔で大吾はふらりと立ち上がり、そのままのそりと勇一の後ろに回った。
「あ、あの……や、安岡さ……ごめ」
あたふたしながら、あわてて勇一が謝ろうとすると、
「田上ちゃん……」
大吾はいきなり勇一の肩に抱きついてきた。
「あんた、ほんっっっとに、野球やったことねえんだな……」
勇一の肩と背中に、ぴったりとくっついた大吾の熱い体温が伝わる。
勇一の体をぎゅっと抱きしめながら、大吾は心底すまなそうな声を出した。
「すまんなぁー田上ちゃーん。俺が無理にお願いしたばっかりに恥かかせちまって。許してくれよぉ」
「い、いや、別に、そんな……」
勇一はあたふたとしながら、大吾の体を振り払おうとしたが、大吾は人懐っこい大型犬のように、勇一の肩口に鼻をすり付けてきた。
「ま、飲んだ飲んだ。今日は俺のおごりだ」
勇一のすぐ近くにある大吾の体からは、きつい酒の臭いと、汗臭さが漂っていた。
それからさらに三時間ほど経ち、『てっちゃん』は閉店時刻となり、勇一たちは店を後にした。
時刻はすでに、深夜の十一時半を回っていた。
大吾は完全に酔っ払って、足腰も立たない状態だ。(もちろん勘定を払える状態ではなく、結局勇一がそれをすべて支払った)
「安岡さんっ、ちょ……こんなとこに座り込まないで……」
勇一がいくら引っ張っても、そこに根が生えたかのように、路地裏から少し出た道路に座り込んだ大吾はそこから動こうとしない。
仕方なく勇一は、九十キロは優にある体躯の大吾を背負い、右に左にとよろめきながらも、とにかく駅前のターミナルまで運んで来た。
そして、ドアが開いた客待ちタクシーの後部座席に、勇一は大吾のでかい尻を両手で押し込めるようにして乗り込ませた。
大吾はこのタクシーで帰らせ、勇一は電車で帰るつもりだった。
「お客さん、どちらへ」
タクシーの運転手はそう聞いてきたが、勇一はふと言葉に詰まった。
「……」
大吾がどこに住んでいるのか、そう言えば一度も本人から聞いたことがない。
『てっちゃん』に戻ってそれを聞こうにも、そうなると終電に間に合わないことはほぼ確実だ。
「お客さんっ、ど・ち・ら・へっ」
あわてて勇一も座席に乗り込み、
「す、すいません、じゃあ、そこの道をまっすぐに行って……」
酒の匂いをぷんぷんさせ、ぐでんぐでんになった大吾を押し出すようにして、勇一はタクシーを降りた。目の前に、勇一が一人住まいをしているアパートがある。
料金を払い、タクシーが去ったあと、勇一は、
「……はあ」
大きくため息をついたあと、いったん大吾を地面に座らせてからまた背負い直し、そのまま一階にある自分の部屋の前まで引きずるようにして運んだ。
また、大吾の体臭が、勇一の鼻先に近づく。
ここまで、二人の距離が近くなったことはこれまでに一度もない。
「……」
勇一はポケットから鍵を取り出して、大吾を外の壁に寄りかからせると先に急いで部屋に入った。
まさかこんなことになるとは思っていなかったので、昨日通販で届いたヒゲクマ系エロDVDも電動バイブもローションも部屋の中に出しっ放しだ。まず、何よりも先にそれらを片づけなければならない。
大吾には――というより、周りの誰にも言っていないが、勇一は同性愛者である。
そして、大吾は、実のところ勇一のかなりタイプの男だ。
だからこそ、万が一にも大吾に手を出して、二人の友情が壊れてしまうのを勇一は恐れていた。
世の中の男すべてがゲイでないことぐらいは、勇一もよく心得ている。
とりあえず、勇一は目についたゲイ関係の「危険物」のみを押し入れの奥に押し込めると、また外へ出た。
そして、意識のない大吾をいったん玄関の中に入れ、靴を脱がせると、洗面所近くの壁にもたれかけさせ、あらためて勇一は部屋に戻り、床に散乱していた雑誌や空のペットボトルなどを手早く片づけた。
そして、大吾を部屋の中に運び込もうと、勇一がもう一度玄関先に戻ると……。
「って、安岡さんっ!」
大吾は、酔ったまま次々と服を脱ぎ散らかし、ブリーフ一丁の下着姿になっていた。
蛍光灯のくっきりとした光に照らし出されたそのいかつい体は、いつもスポーツクラブで見かけるそれとは違い、猥雑な現実感に満ちていた。
とりあえず肩を組むようにして、勇一はベッドまで大吾を運び、その上に大吾を寝かしつけた。
「……」
思わずごくりとのどを鳴らした勇一は、目の前にある大吾の体を隅々まで眺めた。
3.
短く刈り込んだ固めの髪に、昔の学園漫画の番長キャラにも似た太眉とだんごっ鼻、真っ赤な顔を覆う無精ひげ、喉仏の飛び出した首筋、体毛に覆われた太い腕、盛り上がった大胸筋とふさふさと茂る胸毛、そしてやや緩みかけた毛深い腹。
男臭い体とは、こういう体を言うのだろうか。
大吾の全身から、土のにおいのする男の色気が漂っていた。
その下半身には、スポーツクラブの更衣室で見慣れたいつもの白いブリーフがある。汗と陰部臭が入り交じったにおいが立ち上るそれは、股間の一箇所がうっすらと黄ばんでいた。
存在感のある一物がそこに納まっている。
「安岡さん、そんな格好でいると風邪ひきますよ」
軽く、肩を揺すってみた。
が、起きる気配もない。
「……」
ふと、勇一はブリーフに触れるか触れないかのタッチで、そこに、指を置いてみた。
心臓の鼓動が、高まる。
白い生地を突き上げ、こんもりと盛り上がった亀頭の溝の部分を、布の上から指先で、少しこすってみる。
中身が、びくびくと、動いた。
もう、これ以上は危ない。勇一が、手を離そうとしたとき。
「……っ!!」
目をつぶったままの大吾が、勇一の手をがっとつかんで、ブリーフの上にぐにぐにと押しつけた。
「……ちゃんとぉ……しごかんかぃ……」
勇一の刺激で、大吾の一物は、あっという間に、熱く、固く目覚めた。
ブリーフと腹の間から、汗の臭いとともに、半分ほど包皮に包まれた赤黒い亀頭がひょっこりと顔を出した。
勇一の手の中で、熱い杭はびくびくと脈打っていた。
「安岡さん……起きてるんですか」
勇一は、静かに呼びかけてみた。
返答はない。
大吾のブリーフを少しずつ、太股まで降ろしてみた。
もっさりとした陰毛に包まれ、腹に付くほど勃起した大吾の巨砲が姿を現した。
「……」
このでかい一物をしごきたい。
思い切りしゃぶりあげたい。
そんな甘い誘惑が勇一の頭をかすめた。
だが、もしそれをしてしまったら――。
友人を一人失うだけでない、それ以上のやっかいなことが待っているかもしれない。
巨砲をじっと見つめながら、その先の行為をためらっていた勇一の頭を、
「……!!」
突然大吾はがっとつかみ、強い力で自分の腹に引き寄せた。
ぼん、と勇一の顔が大吾のぼってりとした腹の上で跳ね、その唇に大吾の亀頭の先が押し当てられる。
(もう……だめ、だ……っ)
たまらず勇一は、舌先で大吾の亀頭の鈴口をなめてみた。
そこは、すでに塩辛い先走りがにじみ出ている。
勇一はさらに舌を使い、ぺろぺろと尿道の回りをなめ回した。
どんどん先走りの量は増えてくる。
「う、うう……」
太く、低い声で、大吾は快感に悶える。しかし、勇一の頭を押さえ付けているその手の力は、緩むことはない。
「……一年のぉ……坊主の仕事は……まずは……先輩団員のチンポを、しゃぶりあげることから……はじま……」
うわごとのような野太い声が、大吾の口から漏れた。
もしかしたら大吾は大学時代の夢を見ているのだろうか。
勇一は、目の前にそそり立つ、むっとする強いにおいを放つ肉を遠慮がちに口に含んだ。
勇一の唾液とまじり合うと、そのにおいは一層強くなる。
「お……し、いいぞ、ちゃん、と……裏筋、も……」
大吾の命令に従い、勇一はくすぐるように舌先を大吾のその部分にからませた。
巨大な肉棒の輪郭をなぞるごとに、大吾の体がけいれんしたように、びくびくと震えた。
勇一の頭を押さえ付けていた力も、少し緩んだ。
勇一は、大吾のペニスから口を離した。
その奥にたまったもののはけ口を求めて、その熱い肉杭は、ひくひくと震えていた。
「なに……を休ん、どる……次、は……乳首、だろうが」
目をつぶったまま、大吾は命令する。
「……はい」
思わず、勇一は大吾の後輩になったかのように返事をしてしまった。
きっと、大吾はしたたかに酔いつぶれているのだ、そして、どんなことをしても絶対に明日まで目を覚まさないのだ。自分にそう言い聞かせて、勇一は、茂る胸毛の中でぷっくりと飛び出している大吾の右乳首を指でつまみ上げ、こりこりと指先でいじった。
そして、左乳首の頂きを舌の表面のざらざらとした部分でぺろりとなめ上げる。
「あっ……ふ……んんっ……」
大吾の息が荒くなっていった。
舌をとがらせ、大吾の大きめの乳輪の周囲を一周させる。
「もっ……と、気合い、入れてねぶらんかい」
勇一は、舌と左手の指で大吾の褐色の乳首をねちっこく責めた。
「んん……よし……いいぞぉ」
大吾の口から吐息混じりの声が漏れる。
次に勇一が、大吾の脈打っているペニスに右手を置くと、そこは、もうあふれ出る液で先端がべたべたになり、がちがちに反り返っていた。
「貴様も裸になれ……俺が……直々に団の規律を手ほどきしてやる」
勇一はもう、それに逆らおうとさえ思わなかった。
大吾に言われるがままに、勇一は一枚ずつ服を脱いでいった。
そして、すべてを脱ぎ終わった勇一は、大吾のブリーフも引き下ろして全裸にし、その毛深い体の上に重なるように、自分の身を横たえた。
すると大吾は、いきなり勇一の頭をつかんで自分の顔に引き寄せると、その唇に、厚い舌を割って入れた。
べちょべちょと淫らな音を立てて、にゅるにゅると舌をからめてくる。
そのねっとりとした熱い感触は、勇一の体についた欲情の火を、すでに消すことができないほどに燃え上がらせていた。
がまんできずに、うっすらと浮かんだ汗にまみれた大吾の体に、勇一は自分の体をこすり合わせた。
その下半身では、欲望のまま高ぶった二本の肉棒がごりごりと押し当てられている。
勇一は、大吾の顎、首筋、胸、腹をむしゃぶるようになめつくした。
そのたびに、大吾は、獣が唸るような低い声で、悦びの声を上げている。
そして、勇一の舌は、常人以上の重量感をたたえた赤黒い肉の塔にふたたび辿り着いた。
勇一の目の前で、それは、さっきよりもさらに強烈な雄の臭いを放っていた。
勇一は、もうためらわずにその太くて長い棒を思い切り口に含んだ。
じゅぽじゅぽと、出し入れをするたびに卑猥な音が、狭い部屋中に響きわたる。
「う……し……ケツ出せぃ……俺が入れてやる」
4.
勇一は一瞬ためらったが、眉間にしわを寄せて、はあ、はあ、とあえぎ声をあげている大吾の汗で上気した顔が目に入ったとたん、自分の中にわずかに残っていた理性がすべて飛んでしまった。
「返事は……どうした」
「は……はいっ」
そして、勇一はさっき脱いだ服のポケットに手をやり、パスケースの裏に一個だけ忍ばせているコンドームを取り出し、大吾の巨大な性器にそれをかぶせた。
同時に、唾液で濡らした指先で、自分の蕾をほぐし、押し開いていく。
そして準備が整ったところで、大吾の亀頭に照準を合わせ、勇一は、ゆっくりと腰を沈めていった。
「……ああ……っ」
勇一は、その熱い感触に思わず鼻から抜けるような声を漏らした。
「オラ、ちゃんと……腰、振らんかい。我が応援団部の、意地……見せんかい」
「は、はいっ」
腰を振るごとに、大吾の肉棒のエラのくびれが、勇一の中をかき回すように、ぐちゃぐちゃと刺激する。
勇一のペニスも完全にいきり立ち、腰を上下するたびに、大吾のぼってりとした腹の上で、先走りを垂れ流しながら、鎌首を上下左右に振り回した。
大吾のペニスが勇一の前立腺に当たるように、微妙に位置を調節しながら、勇一は激しく腰を動かした。
「うっ……はぁ、んんんっ……」
突き上げる快感に声を押し殺しながら、勇一はあえぎ声を上げた。
大吾は、息を切らしながら、
「だ……団歌……斉唱……」
そう漏らすと、調子っ外れな音程の、獣が威嚇するような声でうなりはじめた。
正義に集う若人よ
希望の空に茜燃ゆ
母校の名誉守り抜き
ここで尽くすぞ我がベスト
いざやその名を轟かさん
その野太い歌声と共に、下から突き上げる大吾の腰の動きはどんどん早くなっていった。
二人の粘膜がこすれ合い、歌に合わせて、まるで伴奏のように、にちゃぐちゅという恥ずかしい音が、大吾と勇一をつなぐ結合部から鳴り響く。
「ぐぉ……ん、ん、んんっ……よし、最後の、仕上げだ、ありがたく、俺の、汁を受け取れっ」
そして、大吾が「うぉぉぉぉぉぉっっ!!」と一声低く叫んだとともに、勇一の中で薄いゴム一枚に包まれた肉棒がびくんと跳ねた。
同時に、勇一もまた、
「あっ……あっ、で、出る……いくぅぅぅぅっっ」
そして、大吾の腹の上に、熱く白いたぎりをぶちまけた。
勇一はそのまま崩れるように、汗みどろの大吾の体の脇に、体を横たえた。
偶然なのか、そうでないのか、目をつぶったままの大吾の右手は、勇一の肩に置かれていた。
二人の男の汗と体臭と精液の生臭いにおいが部屋全体にこもっていた。
「いやあ、すまんなあ。すっかり世話になっちまって」
明けて日曜の朝七時、勇一の部屋で。
大吾は床の上にあぐらをかきながら、小さなテーブルの上に勇一が用意したトーストとゆで卵サラダを大口を開けてぱくついていた。
テーブルをはさんで、勇一はコーヒーをすすりながら、そんな大吾をかすかな脅えとともに見ていた。
大吾の体に残った昨日の痕跡は、すべてタオルで拭き取ってある。だが大吾の記憶までは拭き取ってしまうことはできない。
「ほころへ(ところで)田上ちゃん」
トーストをくわえながら、突然大吾がそう口に出した。
「は、はいっ」
「俺、寝ている時うるさくなかったか」
「いえ……まあ、それほどは……」
「あの後」大吾は、床に毛布を敷いて寝ている勇一の隣で豪快ないびきをかいていたのだが、さすがにそれをそのまま指摘するわけにはいくまい。
大吾は「そうかあ?」と太い腕を組んで、首をかしげた。
「俺、町内会の旅行なんかで誰かと相部屋になると、よく言われんだよな。『大ちゃん、まるで起きてるみてえな寝言言ってたよ』って」
「……!」
よかった、と勇一は心の中で思った。
あれは、やはり全部安岡さんの寝言だったんだ。
それから三十分後、電車で帰るという大吾を勇一は近くの駅まで送っていた。
「田上ちゃん、よかったらまた、草野球の試合に来てくれねえか」
「い、いや、もう野球は……」
「選手でなく、応援でさ」
途中、そんな当たり障りのない話題を交わしながら、二人は駅前にある開店前のひっそりとしたショッピングモールを歩いていた。
が、駅の手前にある旅行代理店の前まで来ると、大吾はふと立ち止まり、
「田上ちゃん、ちょっとションベン……」
そう言って、駅舎の隅にあるトイレに早足で駆け込んだ。
勇一もその後に続くと、その中では、大吾が小便器のかなり手前からズボンのジッパーを下ろし、皮かむりの巨大な陰茎をぽろりと取り出しているところだった。他に利用者の姿はない。
そして大吾は、その先から便器に向けてじょぼじょぼと水っぽい小便を出した。
「……」
昨日の「情事」を思い出し、勇一の顔が熱くなった。
小便を出し終わった大吾は、ぶるんぶるんと筒先を振るうと、それをまたズボンの中にしまった。
そしてせかせかと戻ってきた大吾が洗面所で手を洗ったのを確認して、
「……もういいですか」
と、先に行きかけた勇一に、
「田上ちゃん、ちょっとちょっと」
大吾が声を潜めて、急にそわそわとし始めた。
「どうしたんですか」
「いや、あの……ちょっと忘れ物……な」
そう言って、大きな顔を赤らめている大吾は、きょろきょろと辺りを見回し、誰もいないのを確認すると、突然勇一の目の前に立った。
それから少し屈むようにして、勇一の前にその顔を近づけると、
「……!!」
いきなり、勇一の唇を奪った。
同時に、大吾のごつい右手は、勇一の股間を二、三度ぐにぐにとズボンの上から柔らかく揉んだ。
あまりの突然の展開に固まったままの勇一に、大吾は、へへ、と照れ笑いを浮かべながら、
「ま……また、遊びに来てもいいか。今度は『俺が目を覚ましてるときに』」
「え……あの……」
返事ができないでいる勇一に、
「じゃ、またクラブでな」
そそくさと大吾はホームに向かって小走りに去っていった。
勇一は、唇に残った大吾の感触に気を取られたまま。
ただ、その後ろ姿をぼんやりと見送っていた。